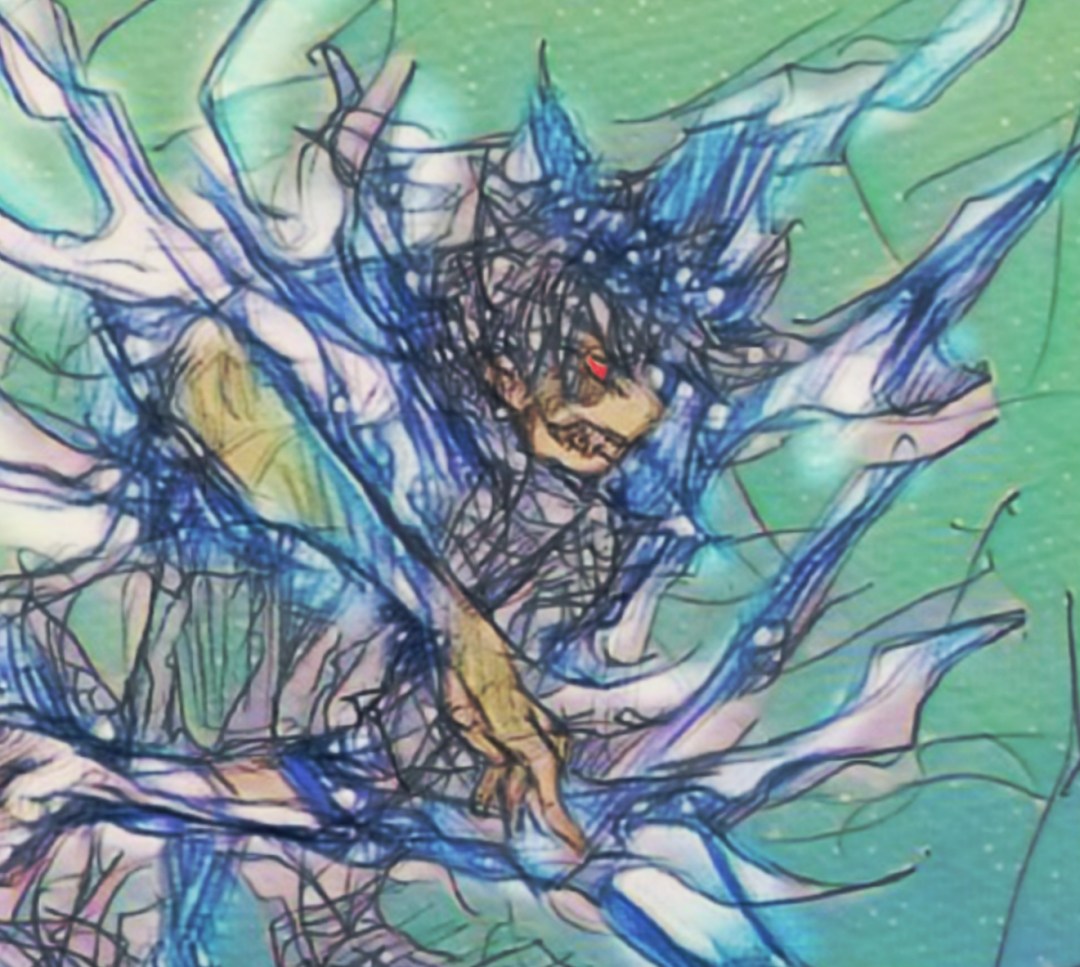5-012(1470)
【サヨの】
ダーザインには、稀族、眷族という二つの階級がある。
始祖の力は、強力で、その血を一滴でも取り込んだ者は、稀族となり不死性を得る。
その稀族でも、ダーザインの能力を使用し続けると真理化、つまり獣に近づく。そのため、身体の部分、一部を人間に戻す必要がある。人間と取り替えるのだ。取替に使われた人間も部分的に不死性を得る。それが、眷族と呼ばれるダーザインだ。
それは、街でも一部の稀族しか知らぬ神聖なる儀式の筈だった。資質ある孤児を三十歳まで育て、才覚のある者は稀族。ない者は眷属として稀族に仕える。
しかし、クロウズは、その儀式を濫用。自身の趣味で、瞳を入れ替え、顔を入れ替え、身体を入れ替えた。そして、爆発的に自身の眷属を量産し街の支配権を拡大した。
さらに、自身の歪んだ欲を満たすためだけの眷属をも作り出した。年端もいかぬ少女を不死者として……。
それが、サヨであった……。
サヨがメフィストを取り込んだ事で、不死力の勢力図が代わる。
ダストが、アズレリィトオンを奏でるオトネと、水晶球の重力を手にするレヴィンに凝縮されていく。
レヴィンは、一歩ずつオトネに近づく。
「大丈夫……もう歌わなくていい」
「ダストは、俺がなんとかするから……」
オトネは、意識が朦朧とするなか、歌をやめようとしない。酸欠で焦点の合わない視線が、レヴィンを捉えた。
【過去の総てを笑い飛ばせ】
【今の総てを愉しめ】
【未来をひとつ決断しろ】
(レヴィン……あなたが教えてくれたこの旋律が、人々を目覚めさせたの。奇跡が起きたの。起こせたのよ。)
ナンジワレトトモニ
(なにもない、なにもできなかった私が、人を救えるなんて……)
(誰かの思惑なんてどうでもいい)
(私に出来ることがある)
(あなたが教えてくれた)
美しい歌声が建物を震わせる。とりまく漆黒のダストがオトネに感銘しつ閃光を放つ。
一瞬の微かな光の煌めきが、レヴィンに確信を与えた。
(やはりな……ダストが黒く見えるのは、物資の存在を引き留め凝縮しているからだ)
(ならば……光を集めることも……)
レヴィンの掌、指輪と水晶球に光が滲みはじめた。
この二つがあっても、オトネの唄を超える事ができていない。
だが、レヴィンには、切り札があった。
それは、ミヅキに託した《血のねがい》だ。
引き寄せたダストがレヴィンの身体に吸収されている。それは、指輪と水晶球の引力。そして、高速回転でさらなる重力が加わった水晶球の力だ。
重力……つまりは、物体同士が引き寄せる引力に回転の遠心力を加えたもの。
「ぐぁああああ……が……っ!!」
繰り返したアレーテウェイン(真理化)によって、ミヅキの両手両足は、原型を留めていない。いや、メフィストの捷さに、人間のカタチではついていけないのだ。
肉体は精神の器。容姿が変われば、中身も変わる。
獣の悪魔に対応する精神……。
《殺す》
《喰い殺す》

(はっ……今、俺はなにを!?)
(やばい……精神が呑み込まれる……)
(だが、このままメフィストに、ダストを吸収させれば、さらにコイツが脅威になる)
(直結しているサヨも意識を乗っ取られるだろう)
(レヴィンに策があるはずだ……血のねがいの意味……)
(しかし、この策は……たが他に手はない……)
(それまで、コイツを足止めしなければ……)
(それすら……このままでは)
目の前に立ち塞がるメフィストは、見せ付けるようにダストを頬張りながら、ミヅキの隙を伺っている。
迷っている隙はない。
「アレーテウェイン!!」
ミヅキは、《血のねがい》を残して、人間としての自我を捨てた。
そして、
【アズレリィトオンがとまる】